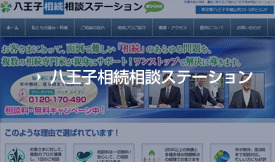代表挨拶
小野登記測量事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。 平成14年に開業してから早いものでお陰様で14年目を迎えました。開業当初より私は土地家屋調査士業はサービス業であるということを念頭に、いつでもご依頼主に喜んでいただくことを第一に考え、フットワークの軽さ、きめ細かい気配り、丁寧な説明、わかりやすい図面の提供等を心掛けてまいりました。 10年ひと昔と言ったのはそれこそ遠い昔の話です。今や5年、いや3年ひと昔と言っても言い過ぎでないほど世の中の流れは早くなっていることを実感します。私どもの業務においても常にアンテナを高く張り、新しい情報をいち早くキャッチするようにし、ご依頼主にフィードバックしていきたいと考えております。今回ホームページを一新し、皆様へ 情報を積極的に発信していくとともに皆様からのお声をより広くから頂戴できるようにしたいと考えております。どうそよろしくお願い致します。
土地家屋調査士 小 野 靖 彦
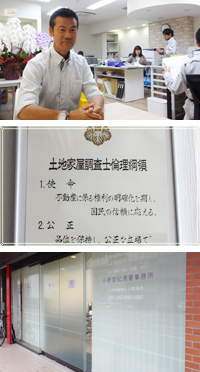

事務所概要
| 名称 | 小野登記測量事務所 (オノトウキソクリョウジムショ) |
| 代表者 | 小野靖彦/東京土地家屋調査士会会員(登録第7096号)八王子支部所属 |
| 事務所所在地 | 東京都八王子市元横山町2丁目6番24号 フジタ八王子マンション102 |
| 連絡先 |
電話番号:042-649-1982 FAX番号:042-649-1983 Eメールアドレス:yasu★onotoukisokuryou.com(★を@に変えて送信ください) |
| 設立 | 平成14年1月1日 |
| 従業員数 | 3名 |
| 業務内容 |
土地家屋調査士業務全般 測量業務全般 開発許可申請 道路位置指定申請許可申請 公共用地払下申請 等 |
| 沿革 |
平成14年 八王子市 土地家屋調査士業開業 民間受注に注力し、八王子市を中心に近県を業務エリアとして、 測量関係では、主に土地売買に伴う境界確認測量、宅地造成に絡む 小・中小規模の宅地開発許可申請手続き、公共用地の払下手続き等を手掛ける。 登記申請関係では戸建の専用住宅を中心とした表題登記から、 大規模な工場、マンション等、幅広く対応し、順調に業績を拡大。 平成20年4月より法務省で進めている登記申請オンライン化に 八王子の土地家屋調査士事務所として、いち早く対応、より迅速な 事件処理を可能にしました。 現在、当事務所では、A2版スキャナーをを導入し、全ての登記申請 添付書類をPDF化してオンライン登記申請システムに対応している。 |
対応業務一覧
下記業務以外にも対応しております。ご相談下さい。
登記関連手続き業務
土地を合筆するとは登記簿上の複数の土地を登記簿上1個の土地にすることです。
現地での見かけ上は間に塀があっても登記簿上は1個の土地である場合もあれば
見かけ上1個の土地でも登記簿上は複数の土地であることがあります。
このように現況と登記簿上は異なっていることもよくあります。
合筆登記は単独ですることもあれば、後で分筆登記をする前提として
合筆登記をする場合もあります。合筆するだけでは測量は必要ありません
が、合わせて測量をする場合もあります。
土地を分筆するとは登記簿上の1個の土地を登記簿上複数の土地にすることです。
相続で遺産分割協議をする前提での分筆、相続税を物納でする前提での分筆、
所有する土地の一部を贈与するため、一部を売却するための分筆等が考えられます。
地積更正登記とは登記簿に記載されている地積(土地の面積)が、実際の地積より
多い、または少ないという場合にする登記手続きです。明治時代には不動産登記の
制度は地租の徴収に主に使われていましたから、本当の面積より少なく申告すると
いうことが行われていました。
ですから、現在でも登記簿面積と実際の面積が食い違っている例が少なくありません。
こういった場合には地積更正登記が必要なり、更正するに当たっては測量が必要で、
測量にあたっては隣接地との境界(筆界)確認が必須となります。
表示登記の目的は不動産の現況をありのまま公示することにあります。登記事項は
法定されており、その中に「地目」があります。これは土地の使用目的により23種類の
地目のうち1種を定めることとなっています。
例えば、建物が建っていれば宅地、道路であれば公衆用道路などです。
現在の地目が宅地である場合に、建物を取り壊して駐車場にした場合には、宅地の
地目を雑種地に変更する必要があります。このように使用状況の変更によって地目を
変更する登記を土地地目変更登記といいます。
ここで注意が必要なのは農地(地目は田または畑)を農地以外の地目にする場合には
農業委員会へ農地法に基づく農地転用許可または届出を申請しなければ
地目変更の登記は認められません。また土地の一部のみの地目が変わった場合には
その部分を分筆したのちに地目変更登記をする土地一部地目変更・分筆登記が必要と
なります。
土地地目変更登記にも申請義務がありますので、地目変更の後1ヶ月以内に
地目変更登記をしないと、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
建物を新築した場合には登記申請義務があり(表題登記は完成後1ヶ月以内にすること
と不動産登記法で定められています。
この申請を怠った場合には10万円以下の過料に処せられます。)、
1ヶ月以内に建物表題登記をする必要があります。
建物の登記事項には、所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者事項など
があり、これらの事項を公の簿冊である登記簿、もしくは、現在ではほとんどが
コンピューター化されていますので登記データへ記載・記録することを「登記」する
といいます。これは何のためにするのかといいますと、この後に続く権利の登記を
どの建物にするかという、権利の客体(目的物)を確定するために行います。
目的物がどこの、どのような、誰が新築した建物かが特定できないと所有権や
抵当権の登記もできないためです。
建物の登記事項の内容を変更した場合には登記申請義務が課されており(表示変更
登記は完成後1ヶ月以内にすることと不動産登記法で定められています。
この申請を怠った場合には10万円以下の過料に処せられます。)、
1ヶ月以内に建物表示変更登記をする必要があります。
建物の登記事項には、所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者事項などが
あり、これらの事項を公の簿冊である登記簿、もしくは、現在ではほとんどが
コンピューター化されていますので登記データへ記載・記録することを「登記」すると
いいます。登記事項については次の欄をご覧下さい。
建物を新築した際には建物表題登記を行いますが、建物の登記事項に変更が生じる
主な場合としては次のようなものがあります。
≪所在地番の変更≫
敷地(建物の底地と言います)の合筆や分筆により建物の所在地番が変更した場合
≪種類の変更≫
店舗を住居とした場合など登記してある種類(用途)が変更になった場合
≪構造の変更≫
屋根を葺き替えた(例えば瓦→スレートへ)
≪床面積の変更≫
増築(この場合には床面積が増えるほか、場合によっては構造も変更となります。
構造が変更となる場合とは例えば従来木造建築だったところへ鉄筋で増築したとか、
2階建てを3階建てとしたような場合です。一部取壊し(全部取り壊しの場合は
滅失登記をします。)附属建物を新築した場合(付属建物の新築は既存建物の
床面積変更の扱いとなります。)
建物を取り壊した際には、取り壊しをした日から1ヶ月以内に建物滅失登記をしなけ
ればなりません。建物滅失登記については所有者または所有権登記名義人に
登記申請義務が課せられていますので、1ヶ月以内に建物滅失登記をしない
場合には10万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
ずっと昔に毀して建物は現存しないのに登記だけが残ってしまっている、
自分が買った土地を役所で調べたら誰だかわからない人の建物の登記があった、
どうしたら良いですか、というようなご相談をよく受けます。
このようなことにならぬよう建物を取り壊したならしっかりと滅失登記をしましょう。
測量関連業務
文字通り現況をそのまま測量することです。依頼主様の指示するポイントで測量し、
概算の面積をお出し致します。隣接地との境界確認は一切行わない一番簡易な
測量です。
面積や土地の形状がわからないので知りたいときには
良いかと思いますが、土地管理上はほぼ意味をなさないと言えます。
隣接する全ての土地との境界を確認した上で測量します(境界を確認するためにも
測量が必要ですが)。民地境界確認に際しては筆界立会確認書を作成し、
隣接地所有者から署名、捺印を頂戴します。官地(公共用地)も同様に
境界確定申請書を提出し、現地立会い境界確認の上、最終的に自治体の長の
公印が押された「公共用地境界確定通知書」(地域、所管によって名称は
若干異なります)を受領します。
土地管理上最も有効な測量です。
土地売却の際など民地のみ境界確認し、公共用地の境界確定はしないということもあります。
関連リンク
当事務所では、お客様へのサービス提供であるという視点に立ち、フットワークの良さ、高いクオリティでの 納品を心掛けております。